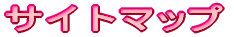
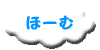
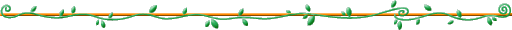

- まず初めに

- 速記とは?
■Q1 速記って何? ■Q2 人の発言っていうのはわかるけど、自分の考えも書き記すってどういうこと? ■Q3 なぜ、速記ができたの? ■Q4 どうして速く書けるの?
■Q5 本当に簡単に覚えられるの? ■Q6 速記の学習って、楽しいの?
- 速記文字とは?
■Q1 速記って、いろんな式があるみたいだけど? ■Q2 「私」という言葉なら、「ワ・タ・ク・シ」と4文字で書くの? 漢字のように1文字で書くの?
■Q3 速記の基本文字って、どんなの? ■Q4 基本文字をよく見ると法則みたいなのがあるように思うけど?
■Q5 速記文字って、単純な線なんだね? ■Q6 清音だけだと、いろんな言葉が書けないけど?
■Q7 それだけでも、まだ書けないよ。「ガ」「カー」「ガー」はどうなっているの?
■Q8 あと、「ン」とか「ッ」とかは、どう書くの? ■Q9 それと、助詞の「を」がないけど?
■Q10 基本文字を覚えると、しゃべっていることは全部書けるの?
- 速記の学習方法
■Q1 速記を習いたいけど、どうすればいいの? ■Q2 教えてくれる場はどうして見つけるの? ■Q3 独習はできないの? ■Q4 速記を勉強するのに何をそろえればいいの?
■Q5 テキストはどうしよう? ■Q6 そのほかに必要なものはないの? ■Q7 どのくらいの期間で速記を覚えることができるの?
- 速記に対する疑問
■Q1 片仮名は画数が少なくて速く書けるけど、速記って言えるのかな? ■Q2 速記って、どのくらいの速さまで書けるの?
■Q3 発言を速記するとき、「あのー」「まあ」とかいう言葉も書くの? ■Q4 「話し言葉」と「書き言葉」って?
■Q5 速記を学ぶと、何か得なことがあるの? ■Q6 速記の資格っていうのはあるの?
■Q7 その検定試験って、どういう方法でやるの? ■Q8 検定試験を受けるにはどうしたらいいの?
■Q9 速記検定試験に合格すると、履歴書の資格欄に書けるの? ■Q10 資格を持っていないと速記の仕事ができないの?
■Q11 プロとして仕事をするには速記検定試験の何級に合格しないとだめなの?
■Q12 速記の需要ってあるの? ■Q13 速記の就職先は? ■Q14 最近よく新聞などの広告に出ているテープライターと速記との違いは?
■Q15 録音機があるのに、今どき速記? ■Q16 最近では、音声入力機なんて言われたりもするけど?
■Q17 器械速記って何? ■Q18 それじゃ、裁判所の速記録はどうなったの?
■Q19 現役で頑張っている速記官は今どのようにしているの?
- 速記の歴史
■Q1 世界で速記が使われ始めたのは、いつごろ? ■Q2 そのころの速記って、今と同じ? ■Q3 それじゃ、日本はいつごろできたの? ■Q4 日本の速記は、だれが考えたの?
■Q5 「速記」っていう言葉は昔からあったの? ■Q6 このHPで紹介している早稲田式は? ■Q7 「速記文字とは?」にあった4大速記方式と言われる方式は?
■Q8 話が変わるけど、速記が文学に与えた影響は大きいって聞いたことがあるけど?
- 速記もろもろ
■Q1 あの歴史上超有名な人物が速記を? ■Q2 現在の超売れっ子作家も、実は速記者だったって?
■Q3 ほかに速記者が出てくる小説はないの? ■Q4 速記者を使って小説を書いていた有名な作家って、だれ?
■Q5 小説やテキストじゃなく、速記に関しての本はあるの? ■Q6 ところで、速記を教えてくれる学校ってどんなところ?
■Q7 専門学校というんじゃなくて教えてくれるところはないの? ■Q8 学校へ通えない人には通信教育もあるらしいけど?
■Q9 自宅学習したいとき、どんなテキストがあるの? ■Q10 そのほかに、参考になるものはないの?
- 速記文字クイズ
- 速記文字文例
- 早稲田式速記マニュアル
■1.清音の書き方 ■2.拗音・半濁音・半濁拗音の書き方 ■3.濁音・長音・長濁音の書き方 ■4.撥音・詰音の書き方 ■5.文章の書き方
- 単語の書き方
■円 ■円の並行法 ■ゆりつぎ ■流し ■正規文字と変規文字 ■そらし ■作角
- 速記方式の比較
■早稲田式 ■中根式 ■V式 ■石村式 ■衆議院式 ■参議院式
- 速記検定に挑戦!
■1.検定試験の実施要領 ■2.6級の内容 ■3.受験のコツ ■4.受験時の持参品 ■5.試験の流れ ■6.合否の採点基準 ■7.合否の通知

- 基本文字/単音
■1.速記文字の書き方 ■2.単曲線の書き方 ■3.複線の書き方 ■4.線の長さ ■5.複曲線の長さ ■6.撥音のついた線の長さ ■7.円の締め方
■8.そらしの書き方 ■9.変規文字の原則 ■10.変規文字の角度 ■11.「イ(ヰ)」の使用例 ■12.撥音を含む単直線の書き方 ■13.撥音を含む複線の書き方
■14.撥音「トン・ハイン・ヤン」等の書き方 ■15.変音の書き方 ■16.長濁音における長音符号 ■17.長母音の書き方 ■18.重音の加点位置
■19.多重音の書き方 ■20.「ウ」と「タイ」の区別 ■21.「ケイ」と「ケー」等の書き方 ■22.「ミュ」の書き方 ■23.「ハ」と「…は」と「ハン」の区別
■24.「ピョ」の書き方 ■25.「ファ・フィ・フェ・フォ」の書き方 ■26.アルファベットの書き方
- 基本文字/単語
■1.線の長さ ■2.円の回し ■3.円の方向 ■4.チョの楕円 ■5.チェの円の回し方 ■6.角度の変化 ■7.ゆずりあいの筆法(例「最愛」)
■8.ゆりつぎの筆法 ■9.作角の筆法 ■10.流しの筆法 ■11.半流しの筆法 ■12.一筆で書ける単語(例「板・火災・屋台・破砕」) ■13.変規文字「ト」を1音目に使う例(例「遠く・遠い・同意」)
■14.変規文字における鋭角選用の原則の例外 ■15.撥音と正規文字(例「漢字・半島」) ■16.詰音の書き方(例「コック」) ■17.詰音と正規文字(例「おって・なって」)
■18.交差しにくい詰音(例「劣勢・列車・発生・月収」) ■19.前後の速記文字を離さずに交差する詰音(例「むっと・釣った」) ■20.「123」の書き方
■21.「リョ…」の書き方 ■22.「リュ…」の書き方 ■23.「…ピョウ」の書き方 ■24.「物価」の「カ」の長さ ■25.「罰金」の濁音符号の打ち方
■26.「給与」と「共有」の書き方 ■27.「お客」と「会釈」の書き方 ■28.「ぼうっと」の長音符号の打ち方 ■29.「精米」の書き方 ■30.「大体大」の書き方
■31.「しまいたい」「体内」の書き方 ■32.「まいない」「ナイマイ」「和裁」の書き方 ■33.「廃止」の書き方 ■34.「プアール茶」の書き方
■35.「キャスト」の書き方 ■36.「決心」の書き方 ■37.「塗って」の書き方 ■38.「ポット」の書き方 ■39.「ぱったり」「ぽったり」の書き方
■40.「…ことと」の書き方 ■41.「ぴょんぴょん」「ぷんぷん」の書き方 ■42.「カチンカチン」の書き方
- 省略法
■1.イ音省略法 ■2.ク音省略法 ■3.ツ音省略法 ■4.二音文字 ■5.助詞 ■6.助動詞 ■7.同行省略法 ■8.ラ行省略法 ■9.上下段使用法
■10.常用句 ■11.常用簡字 ■12.数詞 ■13.外来語 ■14.加点省略法 ■15.依意省略法 ■16.応能省略法
- my省略文字
■1.こういう ■2.こういうこと(こういうこと・こういうもの) ■3.こんな ■4.されている ■5.してきて ■6.なければならない ■7.である
■8.わけ ■9.ている ■10.ならない ■11.いけない ■12.簡字1 ■13.ということ ■14.ことに ■15.簡字2 ■16.いただく
■17.している ■18.簡字3 ■19.について ■20.において ■21.によって ■22.簡字4 ■23.…に関して ■24.…に基づいて
■25.簡字5 ■26.…に比べて ■27.簡字6 ■28.役割を果たす ■29.敬意を表する ■30.支障を来す ■31.必要に応じる ■32.…サイ・ザイ
■33.一(イチ)… ■34.一(イッ)… ■35.簡字7 ■36.簡字8
- 文章練習の仕方
■1.書き出し符号と終了符 ■2.原文帳は1ページ3行に ■3.一かたまり文節単位で ■4.速記文字は常に中央に ■5.原文帳いっぱいに使わないように
■6.原文帳の左下端を常に持つ ■7.速記文字を間違えたとき
- 学習の手引き
■1.原文帳について ■2.シャープについて ■3.練習をする前に ■4.ウオーミングアップをしよう(1) ■5.ウオーミングアップをしよう(2)
■6.説明に耳を傾け、テキストをよく見よう ■7.速記文字を読む練習もしよう ■8.ゆっくりと、丁寧に、正確に書こう ■9.大きく書こう ■10.毎日30分は練習しよう
■11.どこにでも原文帳はある ■12.単音・単語カードをつくろう ■13.単語はどこにでもある ■14.楽しく練習しよう ■15.目標を持とう
■16.単音・単語もしよう ■17.テープを使って練習をしよう ■18.暗書の練習もしてみよう ■19.何度も同じ文章を書いてみよう ■20.速度は少しずつ上げていこう
■21.だれでもスランプはあるもの ■22.反訳もしてみよう
- 反訳の仕方
■1.反訳の練習 (1)反訳練習をしよう (2)反訳は速く終えよう ■2.原稿用紙の使い方 (1)原稿用紙で反訳しよう (2)縦書きで書こう
(3)1升に入れる文字は1字にしよう (4)句読点は行頭に来ないようにしよう (5)適当に改行しよう (6)訂正等には印を活用しよう ■3.表記の仕方
(1)漢字の使用法 (2)平仮名書きの語 (3)片仮名書きの語 (4)現代仮名遣い (5)送り仮名のつけ方 (6)数字の書き方 (7)各種記号の書き方
(8)区切り符号等の用い方 ■4.採点の仕方 (1)1字1失点 (2)誤字等、文字の書く段階でのミス (3)誤訳等、訳す段階でのミス (4)失点対象とならないもの
(5)仮名遣い (6)その他 ■5.合否の判定 (1)合否基準 (2)誤訳率
- 学習アドバイスⅠ
■1.練習法1(大きい字で書こう) ■2.練習法2(基本文字を見直そう) ■3.練習法3(基本文字の連綴練習をしよう) ■4.練習法4(常用語・常用句・常用文を練習しよう)
■5.練習法5(苦手な言葉を整理しよう) ■6.速く書く方法1(運筆を見直そう) ■7.速く書く方法2(シャープをとめずに書こう) ■8.速く書く方法3(崩して書こう)
■9.速く書く方法4(省略文字を使用しよう) ■10.反訳ミスを減らす方法1(聞き漏らさないようにしよう) ■11.反訳ミスを減らす方法2(言葉の感覚を磨こう)
■12.反訳ミスを減らす方法3(正確に書こう) ■13.反訳ミスを減らす方法4(読みかえてみよう) ■14.反訳ミスを減らす方法5(書き損じたらうまく訂正しよう)
■15.反訳ミスを減らす方法6(表記も勉強しよう) ■16.省略文字の使用1(命取りに注意しよう) ■17.省略文字の使用2(活用形も練習しよう)
■18.省略文字の使用3(自分の速記文字をつくろう) ■19.その他1(変規文字を使いこなそう) ■20.その他2(問題により速度感が違う)
- 学習アドバイスⅡ
■1.どんな原文帳がよいか ■2.原文帳にはどんな紙がよいか ■3.どんな速記シャープがよいか ■4.シャープにはどんな芯がよいか ■5.速記文字の長さが区別できない
■6.速記文字が小さくなる ■7.速記文字が左上・左下方向へ走る ■8.原文帳のめくり方が下手 ■9.省略文字がなかなか覚えられない ■10.早くたくさんの省略文字を覚えたい
■11.練習速度に追いつかない ■12.速度練習で引っかかる単語がわからない ■13.速度練習で抜ける箇所が毎回違う
- 速記技能検定試験対策
■ 1.直前の練習 (1)自分の波を知ろう (2)本番と同じ気持ちで練習を (3)反訳は必ず行おう (4)余裕があれば受験級より速い速度での練習を (5)調子が悪いときは書き殴ろう (6)省略文字は余り取り入れないように (7)試験問題を予想しよう (8)本番前日は練習より睡眠をたっぷりとろう (9)場合により受験級をワンランク落とそう ■2.当日の持ち物点検 (1)原文帳 (2)シャープ (3)受験票 (4)その他の持ち物 ■3.当日の注意・点検等 (1)服装に注意をしよう (2)時間に余裕を持とう (3)机を点検しよう ■4.本番での速記 (1)原文帳に余白をつくろう (2)ゆっくり聞こう (3)速記文字は大きく書こう (4)聞きだめはし過ぎないようにしよう (5)抜かす言葉は熟語等にしよう (6)訂正するときは下に書こう (7)要注意箇所に印を入れよう (8)何度も出てくる言葉は省略しよう (9)復唱しながら速記しよう (10)精神を集中させよう (11)空読みは場合により書かないでおこう ■5.本番での反訳 (1)朗読が終わるとすぐにチェックしよう (2)早目に反訳を終えよう (3)文意をつかんで反訳しよう (4)勢いに乗ろう (5)ミスの字数を少なくしよう (6)「標準用字用例辞典」を活用しよう (7)見直しは必ずしよう (8)見直しは反訳のときと反対の方法でしよう (9)時間に余裕があれば反訳原稿を読み返そう (10)読めない速記文字はいろいろな角度から見よう (11)穴を埋めておこう (12)反訳原稿はきれいにしよう ■6.試験を終えて (1)解答書と突き合わせをしよう (2)原文帳と解答書は残しておこう (3)できるだけ受験しよう
- 速記技能検定試験要領
■1.受験申し込み手続 ■2.受験会場と時間 ■3.各級の要領 ■4.受験に当たって ■5.機器使用反訳受験要領 ■6.試験方法 ■7.採点基準
■8.成績優秀者選考基準 ■9.合否通知 ■10.試験会場風景
- 常用語集
- 速記用語
- 早稲田式の歴史
■1.初期の早稲田式 ■2.現在の早稲田式 ■3.早稲田式誕生における特徴 ■4.早稲田式の構成法 ■5.速記文字の特徴 ■6.早稲田式の普及
■7.早稲田式の五大綱領 ■8.早稲田式からの分派
- 速記学習TEXT
■1.早稲田式速記マニュアル(第3版).pdf ■2.覚えよう! みんなの早稲田式速記《基本編》.pdf ■3.「覚えよう! みんなの早稲田式速記」基本文字100.pdf ■4.「覚えよう!
みんなの早稲田式速記」単語一覧.pdf ■5.ランダム練習一覧表.pdf ■6.早稲田式速記法 速記技能検定試験問題常用後〔第2版〕《基本文字編》.pdf
- お知らせ

- 興味ある人からの質問集
- H14.11/H14.12
■Q1 年齢制限/履歴書/学習時間/学習費用 ■Q2 指導場所/学習本
- H15.1/H15.2
■Q3 通信教育/年齢 ■Q4 速記の需要/就職状況 ■Q5 速記とワープロ速記 ■Q6 普通文字での筆記速度 ■Q7 速記者の人数/年収/就業時間
- H15.3/H15.4
■Q8 年齢制限 ■Q9 仕事の有無 ■Q10 衆議院速記者養成所入所に当たって ■Q11 国会での速記/録音と手書き ■Q12 高校の速記部・同好会
■Q13 初心者向けの速記 ■Q14 音符の速記
- H15.5/H15.6
■Q15 就職先 ■Q16 大学と速記の道
- H15.7/H15.8
■Q17 速記の将来/就職先と速記方式 ■Q18 速記専門の大学 ■Q19 速記の覚え方? ■Q20 速記の適応性
- H15.9/H15.10
■Q21 ソーシャルワーカーと速記/大阪で学ぶ場所等 ■Q22 主流な速記方式 ■Q23 速記とテープライター、反訳
- H15.11/H16.1
■Q24 衆議院速記者養成所の受験 ■Q25 男性速記士の数 ■Q26 ステンチュラ/国会のタイプライター/ワープロ速記
- H16.2/H16.3
■Q27 速記検定試験の受験条件/開催日 ■Q28 英文速記の存在 ■Q29 テープライターと速記者 ■Q30 外国語速記の存在と学習方法 ■Q31 国会速記者になるには
- H16.4/H16.6
■Q32 速記学習テキスト ■Q33 国会速記者養成所の受験科目(適性検査) ■Q34 速記検定を受験するに至るまでの学習期間
- H16.8/H16.9
■Q35 速記学習テキストの入手方法 ■Q36 国会速記者になるには ■Q37 速記文字のつなぎ方 ■Q38 省略文字と基本文字の見分け方 ■Q39 基本文字でのメモ
■Q40 すらすら書けるようになるまでの学習期間 ■Q41 大卒者の衆議院速記者養成所への受験 ■Q42 左利きでのハンディ
- H16.10/H16.12
■Q43 速記の仕事/国会速記者の情報 ■Q44 グローバルな速記の仕事 ■Q45 速記者の将来の仕事 ■Q46 話す速度と速記
- H17.1/H17.2
■Q47 速記と進学 ■Q48 6級受験 ■Q49 速記のテキスト本
- H17.3
■Q50 速記の学習方法と年齢
- 学習者からの質問集(速記全般編)
- H15.2/H15.3
■Q1 原文帳のめくり方/原文帳の使い方/テープ練習の仕方 ■Q2 練習教材文章/シャープ ■Q3 間違えて覚えていた速記文字 ■Q4 句読点の採点基準
■Q5 検定試験での採点基準 ■Q6 聞きだめ ■Q7 30分の範囲内での練習方法
- H15.4/H15.5
■Q8 暗書 ■Q9 検定試験の申し込み ■Q10 簡字 ■Q11 筆圧 ■Q12 書き誤り ■Q13 速度練習 ■Q14 文章練習 ■Q15 同文章・同テープの繰り返し学習
■Q16 検定試験での失点
- H15.6/H15.8
■Q17 速記文字の崩し方 ■Q18 書きにくい言葉の対処法 ■Q19 原文帳のつくり方 ■Q20 線の長さ ■Q21 似た速記文字の学習方法
- H15.10/H15.11
■Q22 3級の壁 ■Q23 原文帳と書道半紙 ■Q24 再挑戦する場合の速記能力と年齢
- H15.12/H16.2
■Q25 朗読の仕方 ■Q26 原文帳に使う書道半紙代/速記を生かせる仕事 ■Q27 能率のよい覚え方 ■Q28 プロと省略法/基本文字アとナ、イとマの区別
- H16.3/H16.7
■Q29 共練会(新宿区周辺)の存在 ■Q30 反訳倍数 ■Q31 速記検定試験時の反訳原稿/基本文字での6級受験
- H16.12/H17.1
■Q32 V式学習者さんの学習期間・練習時間《V式》 ■Q33 再勉強/難しい(?) ■Q34 検定試験の中止(?) ■Q35 スランプ(?)
■Q36 基本文字の1分間字数 ■Q37 英語のリスニングがメモ書きできるまでの練習量 ■Q38 筆記用具 ■Q39 速記文字の縦書き ■Q40 原文帳を横長に使うメリット
■Q41 汚い速記文字ときれいな速記文字 ■Q42 授業のノート取り
- H17.3
■Q43 筆記用具
- 学習者からの質問集(速記文字編)
- H15.2/H15.3
■Q1 ファ・チェ・ティの速記文字 ■Q2 ツァ行やスュ・ウィ・ウェ・ウォ等の速記文字/流しの書き方 ■Q3 エ列の加点 ■Q4 外来語の書き方
■Q5 数字の書き方 ■Q6 濁音の書き方
- H15.4/H15.7
■Q7 濃線・加点 【中根式】 ■Q8 中根式の基本文字での速度/重音の書き方 【中根式】 ■Q9 ク・ツ音の省略法 ■Q10 「…スト」の書き方
■Q11 「トR」の書き方 ■Q12 「疑惑」の書き方 ■Q13 佐竹式2音文字と「トヨ」「タヨ」「よろしく…」「どうぞよろしく」「生物」「調節」の書き方
■Q14 「生物多様性」の書き方 ■Q15 「微生物」の書き方
- H15.8/H15.11
■Q16 佐竹式の「チャ・チュ・チェ・チョ・チョウ・チョク・チョン」の書き方 ■Q17 変規文字の使い分け
- H15.12/H16.3
■Q18 「避けて通れない」の書き方 ■Q19 チャとタ、ヒャとヤ、プとヨ、パとワの速記文字
- H16.7/H16.9
■Q20 「なので」の書き方 ■Q21 「タ・チ」と「チャ・チュ」の違い
- H16.10/H16.11
■Q22 「シェ」「ファ」「チェ」「キェ」の基本文字 【V式】 ■Q23 速記文字の角度 ■Q24 繰り返し言葉の書き方 【V式】 ■Q25 活用語尾の書き方
【V式】 ■Q26 「ああいう」の変化形《my省略文字》
- H16.12/H17.2
■Q27 長音の書き方 【V式】 ■Q28 重音の書き方
- H17.9/H17.10
■Q29 「不足や」の書き方 ■Q30 単位の書き方 ■Q31 「不規則」と「複雑」の書き方
- H18.1/H18.5
■Q32 「パイ」と「キョ」、「ロイ」と「ラ」の違い ■Q33 見たこともない速記文字(「はじめに・回り・かぜ」)
- 投稿集
- 1.練習法
■1-1.単語ノートづくり/テープ練習/暗記/気合入れ? ■1-2.テキストの速記文字を丸暗記/日常生活で使用/本読み等
- 2.アガリ解消法
■2-1.受験級より速い速度での練習を/場数を踏む ■2-2.焦りは禁物/40字以上アップの速度練習を/瞬間的に抜かす/場数を踏む
- 3.学習時間
■3-1.学習時間不定/高校時代は約2時間?/速記学校時代は最低2時間 ■3-2.毎日の練習/1日最低30分の練習/楽しく学習 ■3-3.何でもがんがん書きまくろう/1日2時間
- 4.速記の楽しさ・面白さ
■4.1.趣味の段階と道楽の段階 ■4-2.スピードだけじゃない ■4-3.速記文字画
- 5.速記の適不適
■5-1.速記が好きかどうか ■5-2.気が長い等 ■5-3.文字を書くのが好きな人等 ■5-4.やる気のある人
- 6.速記の活用法
■6-1.活用法は探せば幾らでも ■6-2.人のはを書くだけじゃない ■6-3.やっぱりメモ ■6-4.速記中のメモ/名刺等
- 7.速記への夢
■7-1.手書き速記を後世に/インターネットの駆使 ■7-2.速記の普及 ■7-3.宝くじを当てて大々的な速記普及キャンペーン ■7-4.2,1級合格-速記にかける夢は若い人に負けない!-
- 8.速記と年齢
■8-1.年齢はほとんど関係ない/小学生からでも学習可能 ■8-2.夢にかける情熱の前に年齢のハンデーなど吹き飛ばされる ■8-3.余り関係ないが使用する分野で変わる/中高校生ぐらいから始めるのが適当
- 9.練習前の準備
■9-1.基本線の練習 ■9-2.ウオーミングアップ
- 10.速記学習のきっかけ
■10-1.暗号に興味 ■10-2.書店で出会った速記本 ■10-3.雑誌の広告
- 11.基本文字の習得の仕方
■11-1.全体像の把握と識別/模造紙と単語カードを利用 ■11-2.速記文字をなぞる ■11-3.構成原則を覚える/一覧表や単音カードの作成/練習量をふやす
■11-4.繰り返し書く
- 12.速記に出会えてよかったこと・よくなかったこと
■12-1.生き甲斐・事務能力倍増等/中傷 ■12-2.時間の短縮・国語力/便利屋・漢字能力低下 ■12-3.町内会の回覧板作成 ■12-4.悪い遊びを覚えなかった・パソコン等との縁等
- 13.手の動きと速記の適性
■13-1.気にしないでよい/腕全体で書く ■13-2.速記が好きかどうか ■13-3.手の速さより反射神経・書くリズム ■13-4.気にしない/速記が好きであること
- 14.検定試験直前の練習方法
■14-1.速度・反訳・単音・用字練習/問題予想/体調調整
- 15.高校・大学での部活
■15-1.我が高校速記部の活動
- 16.初級スランプ脱出策
■16-1.やはり基本文字練習が一番!
- 17.独習のメリット・デメリット
■17-1.やる気次第でメリットにもデメリットにも
- 18.速記方式の選択法
■18-1.偶然の出会い ■18-2.指導者・学習者数・テキスト
- 19.文章練習時の題材
■19-1.歌を聞きながら詩の書き取り ■19-2.検定問題/国会会議録/新聞
- 0.その他
■0-1.夏の受験対策
- 速記活動等
- Link

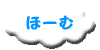
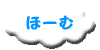

![]()
![]()
![]()